高圧受電設備では、地絡事故の検出が非常に重要です。
地絡検出に使われる代表的な保護継電器には、
- 地絡継電器(GR)
- 地絡方向継電器(DGR)
の2種類があります。
本記事では、
ZCT(零相電流)・ZPD(零相電圧)の原理から、
ケーブル長による誤動作の理由、
方向性継電器が必要になる距離の考え方まで、実務目線で解説します。
地絡継電器(GR)の基本原理
ZCT(零相電流)による地絡検出
一般的な地絡継電器は、ZCT(Zero-phase Current Transformer:零相変流器)を用いて地絡を検出します。
- 三相電流(R・S・T)を一括で検出
- 正常時:三相電流のベクトル和=0
- 地絡時:差分電流(零相電流)が発生
この零相電流が設定値を超えると、地絡と判断して動作します。
地絡方向継電器(DGR)の仕組み
ZCT + ZPD による方向判別
地絡方向継電器は、
- ZCT(零相電流)
- ZPD(零相電圧)
の両方を使って動作します。
零相電圧(ZPD)とは
零相電圧は、
中性点に電圧が発生しているかどうかを検出しています。
- 地絡がない → 中性点電圧なし(OVなし)
- 地絡がある → 中性点電圧が発生(OV発生)
この零相電流と零相電圧の位相関係から、
- 地絡が一次側(自設備側)
- 地絡が二次側(負荷側)
のどちらで起きているかを判別できるのが、
地絡方向継電器の最大の特徴です。
ケーブルが長いときは地絡方向継電器
一般的には50mを超えるとき、もらい事故(電力側の地絡)防止の観点からも。
なぜケーブルが長いと誤動作しやすいのか
静電容量電流の影響
高圧ケーブル(CVTなど)には静電容量があります。
ケーブルが長くなるほど、地絡していなくても零相電流が流れるようになります。
無方向地絡継電器が誤動作する距離の計算例
条件
- ケーブル:CVT 38sq
- 地絡継電器整定値:200mA
- 周波数:50Hz
- ケーブル静電容量:0.32 μF/km
- 系統電圧:6.6kV
計算式
0.2 = (6600 / √3) × 2π × 50 × 3 × (0.32 × 10⁻⁶) × X
これを解くと、
X = 0.174 km = 約174 m
つまり、約174mで継電器が動作してしまう計算になります。
しかし、実務では、
- 製品誤差
- 温度・劣化
- 不平衡電流
などを考慮する必要があります。
👉 安全率1/3を取ると約50m
85mを超えると誤動作しやすい理由
- ケーブル静電容量による零相電流が増加
- 無方向SOGでは「地絡」と区別できない
- 微小な不平衡でも整定値を超えやすい
特に85m以上になると、
誤動作・不要動作のリスクが一気に高まります。
高圧ケーブルのシールド接地と注意点
基本ルール
- 100m未満:片側接地
- 100m以上:両側接地
両側接地の注意点
両側接地をすると、
シールド線に循環電流が流れます。
この循環電流が、
- ZCTを通過
- 地絡電流と誤認
することで、誤動作の原因になります。
👉 シールド線は必ずZCTを通さずに戻す
👉 ZCTを貫通させない配線が重要です。
地絡継電器の設置実務の考え方
- 通常の受電設備
→ SOGで一括監視 - 高圧で他設備へ送電する場合
(サブ変電設備・高圧機器など)
→ 送り出し回路ごとにZCT・DGRを設置
ZCTはメーカー混在に注意
ZCTはメーカーごとに、
- 感度
- 飽和特性
- 位相特性
が異なります。
そのため、
ZCTだけ別メーカーにすると、動作電流がズレる
というトラブルが起こりがちです。
👉 継電器とZCTは同一メーカーで統一
👉 仕様書の「適合ZCT」を必ず確認
まとめ
- 地絡継電器:ZCTで零相電流を検出
- 地絡方向継電器:ZCT+ZPDで方向判別
- ケーブルが長いほど静電容量電流が増える
- 50m以上は方向性継電器が安全
- シールド接地・ZCT配線は誤動作対策の要
- ZCTのメーカー混在は要注意
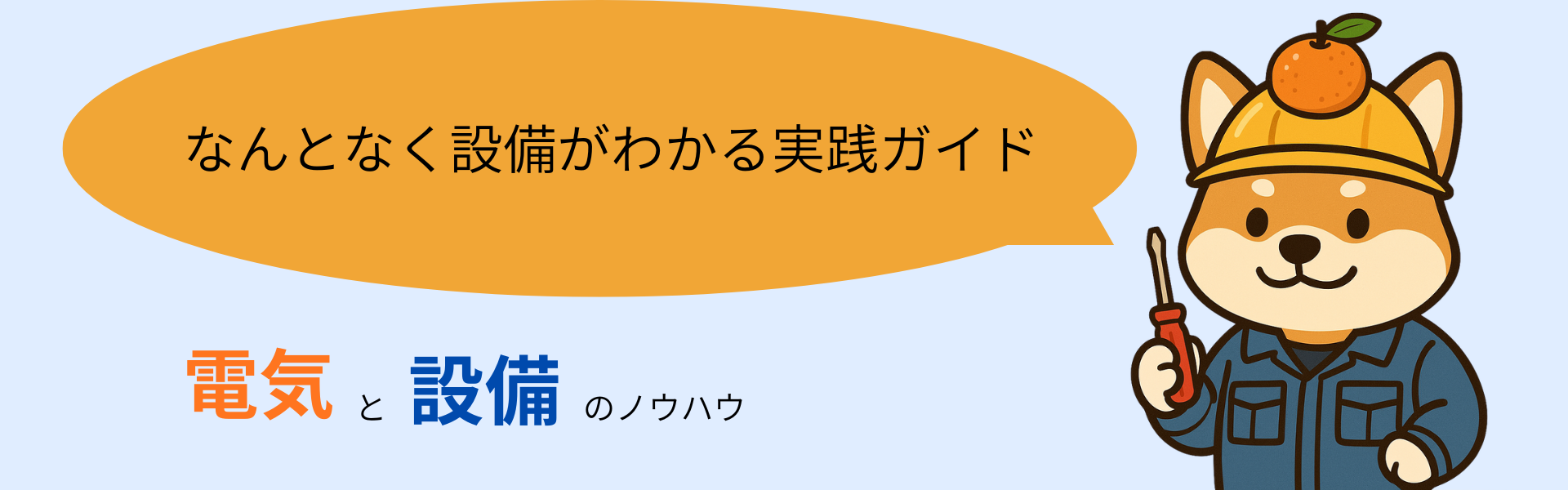



コメント