建物の安全を守るために設置される避雷針や避雷導体。
特に高さが20mを超える建物や、危険物を指定数量以上取り扱う施設には、法律上設置が義務付けられています。
また、法律で義務がなくても、雷の被害を受けやすい地域や重要施設では、リスクを減らす目的で任意に設置されるケースも少なくありません。
今回は、この避雷設備の目的や方式、さらに新たに設備を設置する際の注意点について、分かりやすくまとめます。
避雷設備の目的とは?
避雷設備は、建物に落雷があった場合にその電流を安全に大地へ流し、
建物の構造物や内部設備への被害、さらには火災を防ぐために設置されています。
雷の放電エネルギーは非常に大きいため、適切に地面へ逃がす仕組みが重要です。
避雷設備の設置が義務付けられるケース
- 建築基準法
建築物の高さが20mを超える部分には、避雷設備の設置が必要です。
看板や屋上設備なども、その高さに含まれます。 - 消防法
危険物を指定数量以上に取り扱う建物(ガソリンや可燃性ガスの貯蔵施設など)は、
落雷による火災を防止するため、避雷設備が義務化されています。 - 任意設置
データセンター、病院、工場など、万一の被害を防ぐ必要性が高い施設では、
法的義務がなくても避雷設備を設置するケースが多いです。
避雷設備の方式
避雷設備の方式には、大きく分けて次の2種類があります。
1. 避雷針方式
建物の屋上に避雷針を立て、その先端から周囲に保護範囲を設定する方法です。
保護範囲は「保護角法」と呼ばれる考え方に基づき、
- 低層(20m以下)の場合は最大53°程度
- 高層になるほど保護角が狭くなる
というルールがあります。
避雷針の保護範囲から外れてしまう部分については、追加の避雷導体などで保護します。
2. 避雷導体(メッシュ方式)
建物の屋上に導線を一定の間隔で張り巡らせて保護する方式です。
いわば屋上を「雷から守る金属の網」で覆うイメージになります。
このメッシュの間隔は保護レベル(LPL)によって変わり、
例えば保護レベルIIIであれば最大15m程度、保護レベルIVなら20m程度まで広げられます。
引下げ導体は、通常建物の周囲50mごとに1本以上、かつ2箇所以上設置し、
屋上のメッシュから接地極までつなぎます。
導体の断面積は
- 銅の場合14mm²以上(通常30mm²推奨)
- アルミの場合22mm²以上
が必要とされています。
接地抵抗は10Ω以下にするのが原則です。
設備を後から設置するときの注意点
建物の避雷設備が完成した後に、新しく設備(看板やアンテナなど)を設置する場合は注意が必要です。
- 避雷保護範囲からはみ出さないこと
設置した設備が避雷針や避雷導体の保護範囲から飛び出してしまうと、
そこが落雷を受ける危険性が出てきます。
はみ出す場合には、新たにその設備も含めた避雷対策を検討する必要があります。 - 避雷設備の近くに金属体を置かないこと
避雷設備の引下げ導体や接地極から1.5m以内に金属体を設置すると危険です。
雷の電圧はとても高く、側雷(飛び移り)が起こる可能性があります。
やむを得ず金属体を近くに設置する場合は、同電位に保つために
14mm²以上の銅線(または22mm²以上のアルミ線)で等電位ボンディングを行いましょう。
まとめ
避雷設備は、建物を落雷被害から守る大切な防災設備です。
建物の高さや取り扱う危険物の種類によっては法律で設置が義務化されており、
それ以外の施設でもリスク管理のために導入するケースが増えています。
また、避雷設備がすでにある建物に新しく設備を取り付ける際には、
保護範囲や金属体の配置などに十分注意し、必要があれば電気工事の専門家に相談するのがおすすめです。
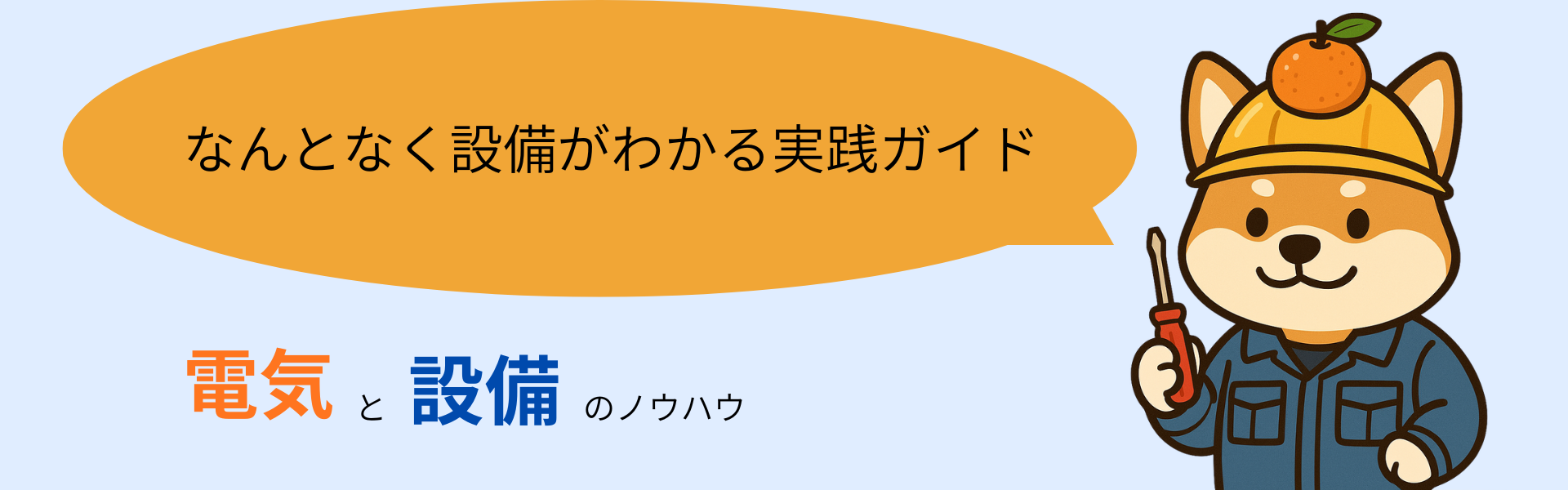
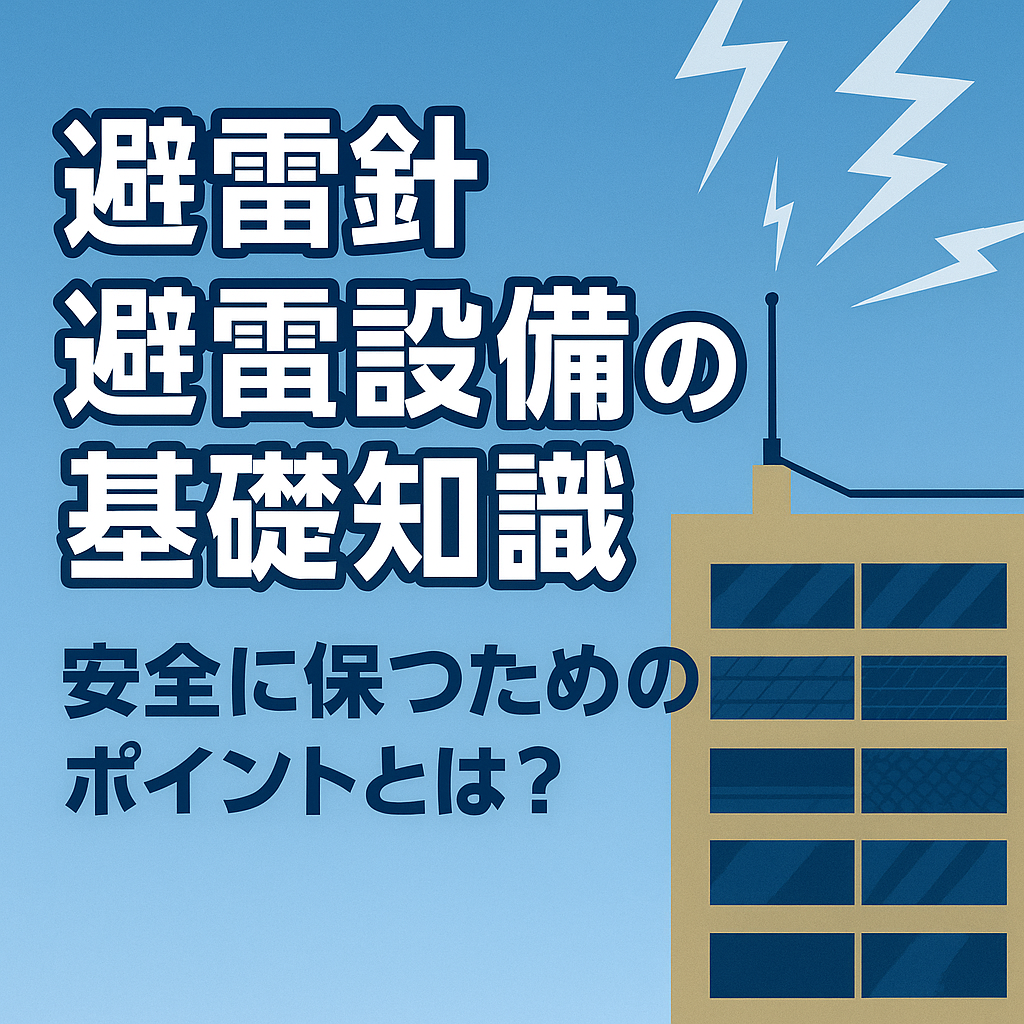

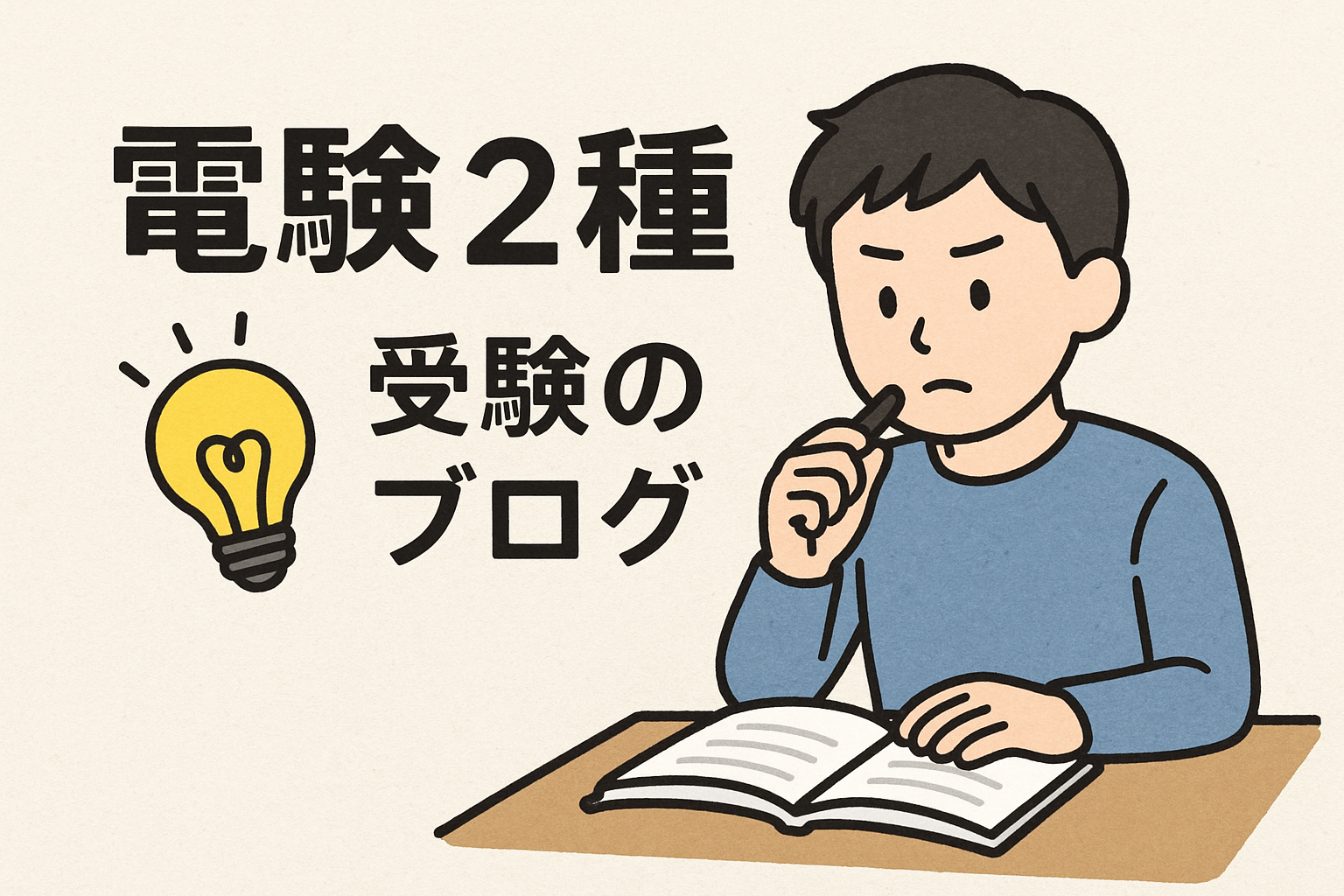
コメント