🔹 コンクリートの配合計画とは
コンクリートの配合計画とは、設計で求められる強度を確実に満たすための配合(セメント・水・骨材などの割合)を決める作業です。
現場で打設されるコンクリートは、気温や施工条件によって強度の発現が変わるため、設計段階で補正(マージン)を見込む必要があります。
🔹 設計強度と指定強度(予備強度)の違い
まず、コンクリートには次の2つの「強度」があります。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 設計強度 | 構造計算や耐久性の観点から、設計上必要とされる強度 |
| 指定強度(呼び強度) | 実際にコンクリートを発注するときに指定する強度(設計強度に余裕を見込む) |
コンクリートの強度は通常、20℃で28日間養生したときの圧縮強度を基準にしています。
しかし実際の現場では気温が変動するため、設計強度を確保するには「季節補正」が必要です。
🔹 季節による強度補正(+6、+3の理由)
気温が低いと強度の発現が遅くなり、設計強度を満たせない可能性があります。
そのため、次のように季節によって指定強度を上乗せするのが一般的です。
| 季節 | 補正値 | 補正の目的 |
|---|---|---|
| 冬期(低温期) | +6 N/mm² | 養生温度が低く、強度発現が遅れるため |
| 中間期(春・秋) | +3 N/mm² | 気温変化があるため、軽度の補正を行う |
| 夏期(高温期) | +6 N/mm²(例) | 打込み後の温度上昇や急激な乾燥による強度低下を考慮 |
つまり、「予備強度」は20℃・28日養生で保証される数値ですが、現実の現場では温度や湿度が一定ではないため、補正をして設計強度を担保するわけです。
🔹 コンクリート発注時に指定する内容
コンクリートを生コン工場に発注する際は、次の項目を明確に伝えます。
- 指定強度(例:21、24、27N/mm²)
→ 強度は3刻みで指定するのが一般的(18・21・24・27…) - スランプ(例:15cm)
→ 流動性の指標。高いほど施工しやすいが、強度が低下しやすい。
標準仕様ではスランプ15cmがバランス良好です。 - 骨材の最大寸法(例:20mmまたは25mm)
→ 鉄筋が密な場合は20mm、一般的な基礎部では25mmを使用することもあります。
🔹 スランプ値の考え方
スランプとは、コンクリートの「やわらかさ」を表す値です。
スランプが大きいほど流動性が高く、型枠や配筋間に流れ込みやすくなります。
ただし、スランプが高すぎると材料分離や強度低下の原因になるため、スランプ15cm程度を標準に指定するのが安全です。
| スランプ値 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 12cm以下 | 硬めで流動性が低い | 床版・道路・打込み条件が良い現場 |
| 15cm | 標準的で扱いやすい | 基礎や一般構造物 |
| 18cm以上 | 流動性が高いが分離しやすい | 密配筋部、ポンプ圧送時(混和剤使用時) |
🔹 骨材の最大寸法の選び方
骨材(砂利・砕石)の最大寸法は、配筋間隔や打込み性で決めます。
| 最大寸法 | 特徴 |
|---|---|
| 20mm | 細かく、配筋の密な部分に適している |
| 25mm | 粗く、広い基礎や厚いスラブに適している |
骨材が「砂利」か「砕石」かは、見た目や形状(丸い/角張っている)による違いであり、寸法の違いそのものではありません。
🔹 設計強度の決め方
設計強度は、構造物の用途・耐用年数・環境条件で決まります。
一般的な建築物や設備基礎では 21N/mm²以上 を使用するケースが多く、耐久性の確保や中性化対策にも有効です。
ただし、軽構造や一時的な基礎では18N/mm²程度でも十分な場合もあります。
🔹 まとめ
- 設計強度は「構造的に必要な強度」
- 指定強度(呼び強度)は「設計強度+季節補正」
- 発注時には「強度・スランプ・骨材寸法」を必ず指定する
- スランプは施工性と強度のバランスを見て15cmが標準
- 骨材寸法は配筋の密度と打設条件で決める
コンクリートの品質は「現場での温度・養生管理」でも大きく変わります。
配合計画を正しく理解しておくことで、設備基礎の品質と耐久性を確保できます。
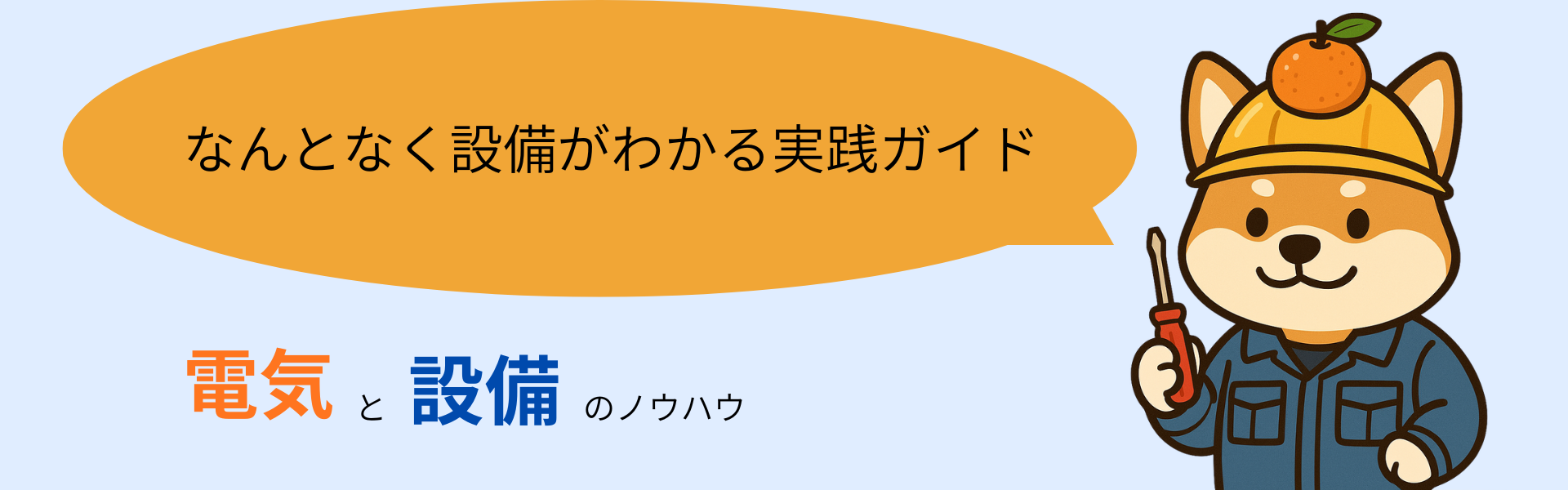
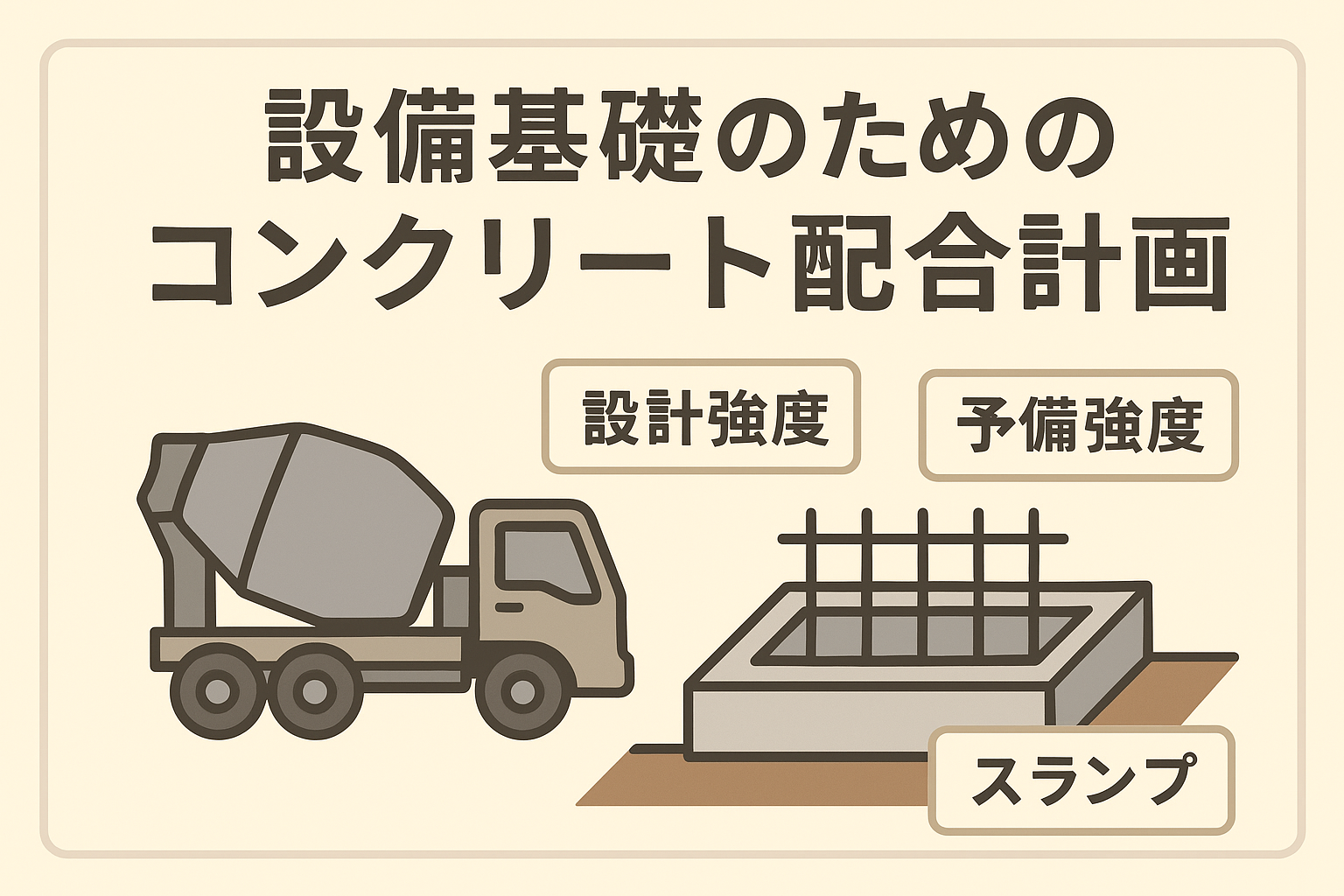
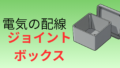
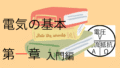
コメント