絶縁測定結果が正常でも漏電ブレーカーが作動する理由とは?
電気設備の点検をしていると、絶縁抵抗値に異常がないにも関わらず、漏電ブレーカー(漏電遮断器)が動作してしまうというケースに遭遇することがあります。今回はその原因と対策について解説します。
漏電ブレーカーの仕組み
漏電ブレーカーには**ZCT(零相変流器)**が内蔵されています。このZCTは、回路に流れる「行き(L)」と「帰り(N)」の電流の差(=漏れ電流)を検知するものです。
正常であれば、LとNの電流は等しく、ZCTには何も検出されません。しかし、何らかの理由で電流が大地などへ漏れると、その差をZCTが感知し、遮断動作が行われます。
※テストボタンは、このZCTに擬似的な漏電を発生させることで、正常に作動するかを確認しています。
絶縁抵抗測定が正常でも動作する理由
漏電ブレーカーが動作したのに、絶縁抵抗測定では異常が出ない――この現象の多くは測定環境や条件の違いによって説明がつきます。
雨や湿気が影響する
たとえば、雨の日や湿度の高い日には、機器や配線の表面に湿気が付着し、絶縁性能が一時的に低下することがあります。このとき、微弱ながら漏電電流が発生し、漏電ブレーカーが作動することがあるのです。
このような状況を再現するには、実際に雨の日や湿度の高い日に絶縁抵抗測定を行うことが有効です。
測定者の状態も影響
また、測定時に作業者の手が湿っていたり、汗をかいていると、テスターのリードや機器に微妙な電流が流れる可能性があります。
正確な絶縁抵抗測定のためには、絶縁手袋を着用し、測定時の接触を最小限にすることが重要です。
数値で見る漏電の可能性
100V回路の絶縁抵抗の基準値は**0.1MΩ(100kΩ)**です。
このときに流れる電流は以下の通りです:
100V ÷ 100,000Ω = 0.001A(1mA)
漏電遮断器の感度電流が15mAのものであれば、この値は作動しない範囲にありますが、7.5mA(定格の1/2)以上の電流が流れると動作する可能性があるとされています。
つまり、湿気などで一時的に絶縁抵抗が0.01MΩ(10kΩ)まで下がれば、10mAの漏れ電流が発生し、遮断器が動作する可能性が高くなります。
まとめ
- 絶縁抵抗が基準を満たしていても、環境条件(雨・湿気・汚れ)によって漏電が発生することがある
- 測定時には絶縁手袋を使用し、正しい測定環境を整えることが重要
- 実際にブレーカーが作動した日と同じような環境で測定を行うと、再現性が高まる
絶縁測定結果だけに頼らず、実際の運用環境を意識した点検と対策が、安定した設備運用につながります。
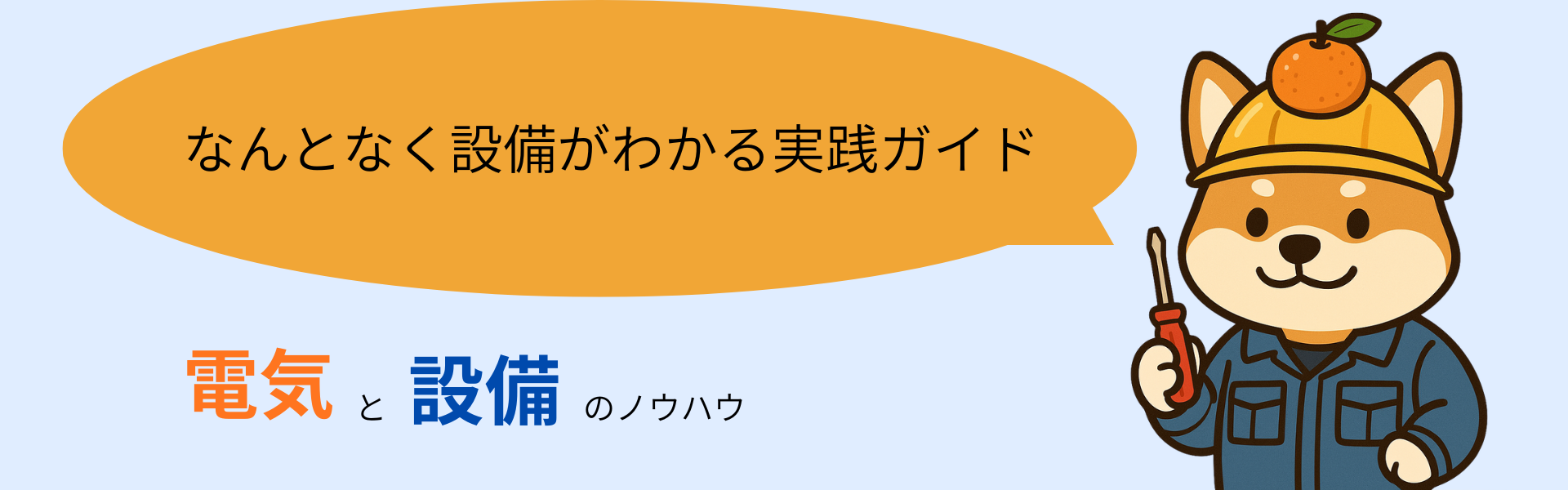


コメント