電気工事に使う配管の種類(CD管・PF管・VE管・FEP管・金属管など)の特徴や使用場所、太さの選定基準をわかりやすく解説。占有率や曲がり角度、ハンドホールの設置距離など施工の基本ルールもまとめています。
1. 電気工事で使う配管の種類
電気配管にはさまざまな種類があり、それぞれ使用できる場所や特徴が異なります。代表的な配管を整理してみましょう。
CD管(合成樹脂可とう電線管)
- 自己消火性がないため、コンクリート内の隠ぺい配管専用。
PF管(合成樹脂可とう電線管・難燃性)
- 種類が多く、一般的な屋内外で幅広く使用可能。
- 屋外では二重管を使用。
- 太陽光発電ではMFタイプが推奨される。
VE管(硬質ビニル電線管)
- 屋内外で一般的によく使われる。
- ただし高温環境や直射日光下には不向き。
FEP管(ポリエチレン電線管)
- 埋設配管によく使用。
- 屋外でも使用可能だが、外観上あまり好まれない。
金属管の種類
- E管(イージー管):ネジなしタイプ。屋内専用。屋外は不可。
- C管:ネジ付きタイプ。密封性が高く粉塵環境に強い。施工はやや難しい。
- G管:屋内外で使用可能。付属品の取り付けが必要だが、防爆エリアにも対応。
金属可とう電線管
- 屋内用・屋外用の両方がある。
- 防爆エリアでは使用不可。
2. 配管の太さ(管径)の選び方
配管の太さは、電線かケーブルかによって選定方法が変わります。
電線を収める場合
- 基本は配管内占有率 32%以下。
- ただし、断面積 8mm²以下の電線で、同一サイズ・通線容易な場合は48%まで可能。
- 露出配管は通線が容易なため48%でもよいが、埋設の場合は32%が望ましい。
| 公称断面積(㎟) | 仕上がり外径(mm) |
|---|---|
| 8 | 19 |
| 14 | 21 |
| 22 | 24 |
| 38 | 28 |
| 60 | 33 |
| 100 | 41 |
| 150 | 47 |
| 200 | 55 |
| 250 | 60 |
| 公称断面積(㎟) | 仕上がり外径(mm) |
|---|---|
| 3.5 | 6.3 |
| 5.5 | 7.0 |
※仕上がり外径はメーカー・仕様(難燃・耐熱など)により若干異なります。 正確な寸法は各メーカーの技術資料をご確認ください。
ケーブルを収める場合
- 1本のみ:ケーブル外径 ×1.5以上の内径を持つ管を選定。
- 複数本の場合:電線と同じく占有率を基準にする。
🔧 配管サイズ自動選定ツール(PF/VE/E管)
※管内径は代表値です。PF管は可とう性・曲がりにより実効占有率が低下するため、 32%での設計を推奨します。最終判断は内線規程・メーカー資料をご確認ください。
3. 配管施工の基本ルール
曲がり
- 1区間あたり4箇所以内、総角度270°以内。
- 通線の難易度はノーマル1箇所で2倍 2箇所で4倍 3箇所で8倍
配管長とボックス設置
- 通常は30m以内にジョイントボックスを設ける。
- 埋設の場合は30m以下、最大でも50m以内にハンドホールを設置。
金属管の接地
- 金属管は電線種別に応じて接地工事(アース)が必要。
- 接地線の太さは、電流の約0.0019倍を目安に選定(内線規程を参照)。
まとめ
電気工事で使用する配管は、種類ごとに特徴や適した使用場所が決まっています。
- CD管はコンクリート内専用
- PF管は汎用性が高く、屋外や太陽光にも対応可能あ
- VE管は屋内向けだが熱や直射日光に弱い
- 金属管は耐久性や防爆性に優れるが、接地工事が必要
さらに、配管の太さは「占有率」「ケーブル外径」「施工条件」に基づいて選定します。
正しい管種とサイズを選ぶことで、施工性・安全性・耐久性が大きく向上します。
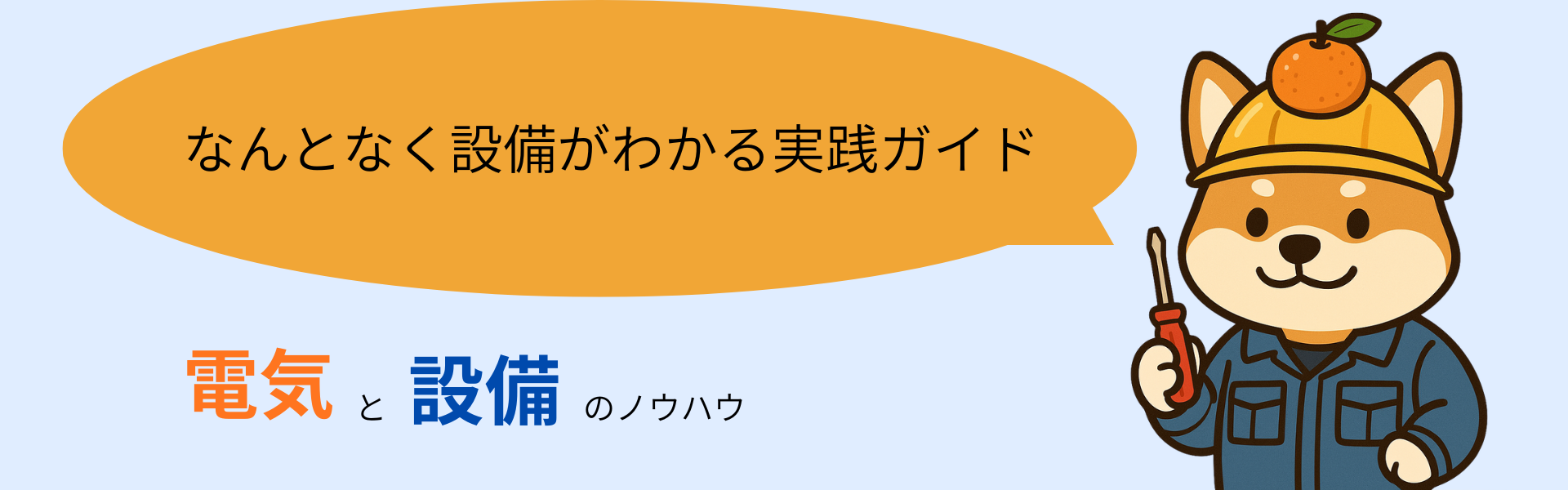
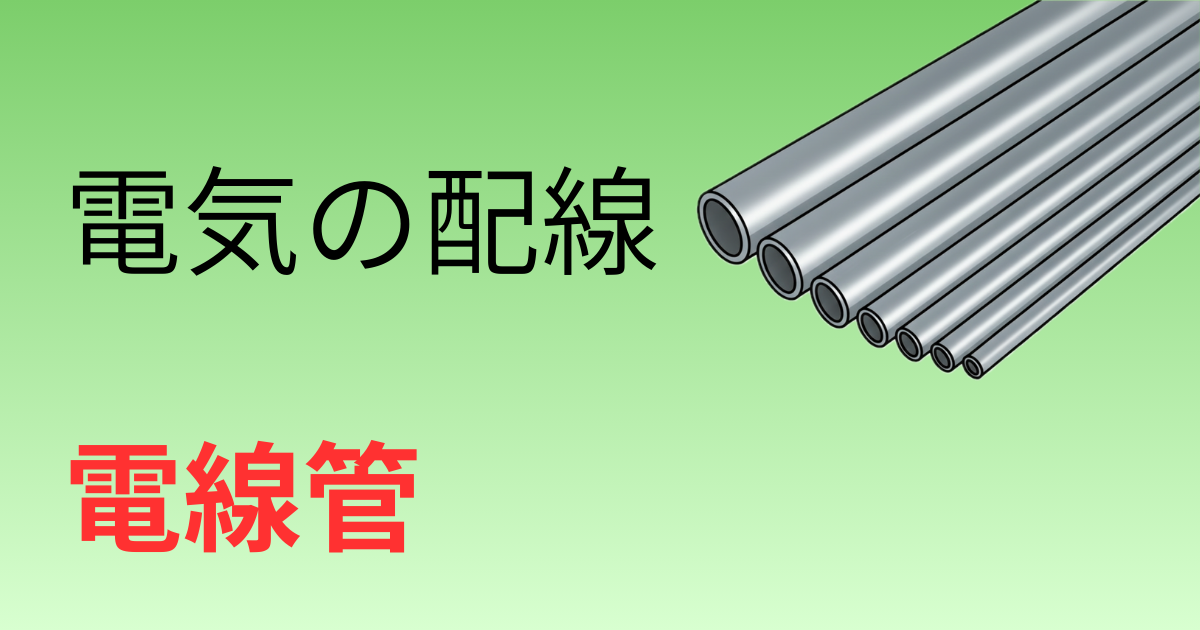
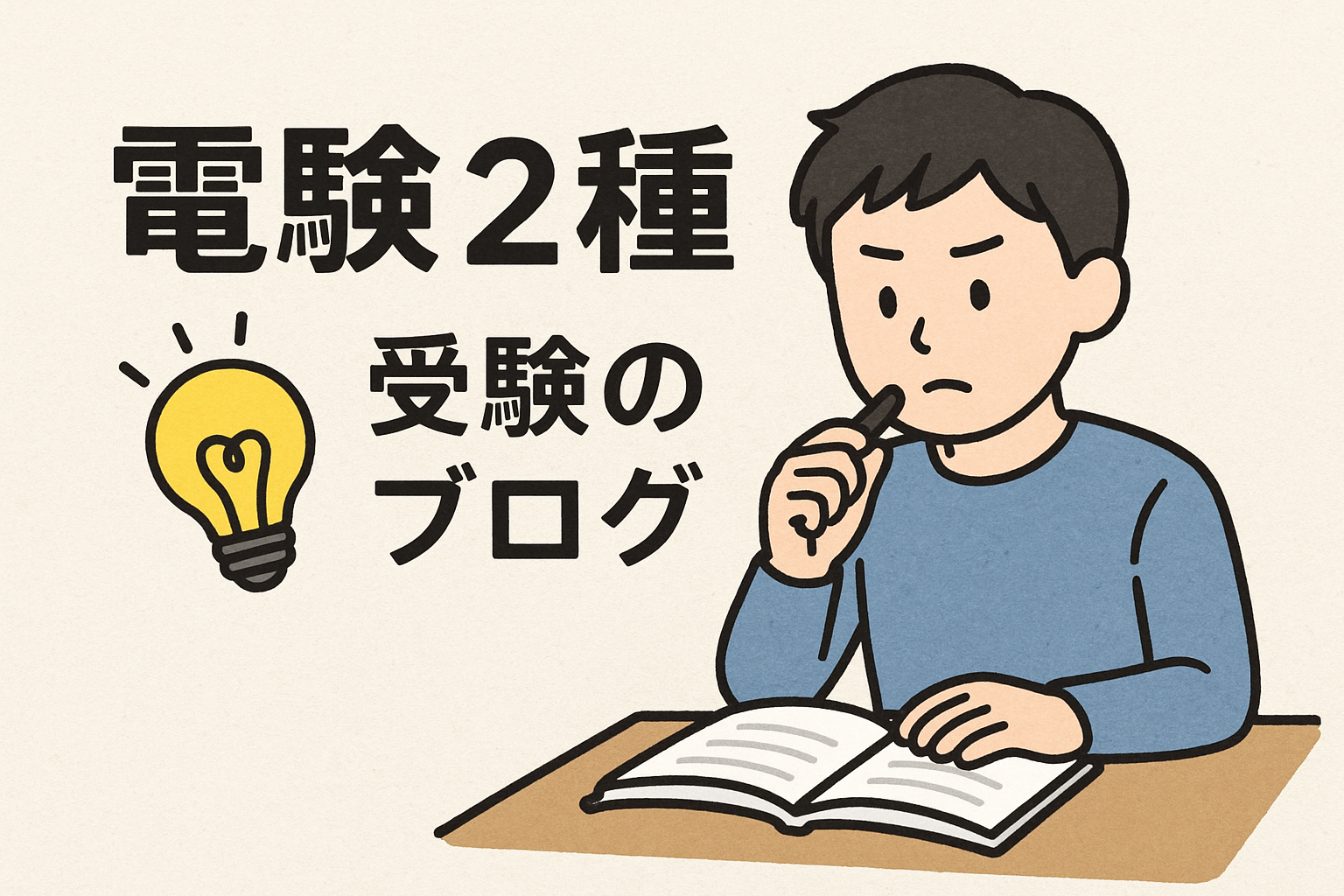

コメント