電気をたくさん使う事業者や施設では、「高圧受電設備」の導入が求められることがあります。
この記事では、導入基準や費用、メリット・デメリット、点検義務までをわかりやすく紹介します。
高圧受電設備の導入基準
一般的に、契約電力が50kWを超えると、電力会社から高圧で電気を受ける「高圧受電設備」の設置が必要になります。
ただし、一時的に50kWを超える程度であれば、電力会社との協議によって対応が異なることもあります。
そのため、継続的な使用状況をもとに判断されます。
高圧受電のメリット:電気代が安くなる
最大のメリットは電力単価の安さです。
| 契約形態 | 電力単価(目安) |
|---|---|
| 高圧受電 | 約19円/kWh |
| 低圧契約 | 約24円/kWh |
使用電力量が多い場合は、高圧受電の方がトータルの電気料金を抑えられることになります。
デメリット① 設備を所有する必要がある
高圧受電にするためには、専用設備の設置と所有が必要です。
また、受電用の電柱や、そこに**柱上負荷開閉器(SOG)**を設置する必要があります。
この柱から先が電力会社と自社の責任分界点となり、
以降の設備のトラブルが原因で停電が発生した場合には、**周囲への波及事故(地域停電)**と見なされ、損害賠償の責任を問われる可能性もあります。
デメリット② トランスやキュービクルが必要
高圧(6600Vなど)で受けた電気を、通常の動力や電灯で使える低圧(200V・100V)に変換するためには、**トランス(変圧器)**が必要です。
このトランスなどを一体化してコンパクトに設置できるのが、
キュービクル式高圧受電設備です。
キュービクルの種類と制限
キュービクルは大きく分けて以下の2種類があります:
- PFS(LBS)型
- CB型(VCB)
さらに、300kVAを超える設備の場合は「CB型(VCB)」を使用することが義務づけられています。
VCBは遮断性能が高く、真空中でアーク(火花)を消すため、安全性が高いのが特徴です。
主遮断器はVCBでなければなりませんが、それ以降の遮断器については制限されていません。
定期点検と電気主任技術者の配置義務
高圧受電設備は、法令により定期点検が義務づけられています。
そして、その点検を行うためには**「電気主任技術者」の資格保有者を選任**しなければなりません。
- 自社で点検している場合:第三種電気主任技術者の免許不要
- 外部に点検を委託する場合:第三種電気主任技術者の免許を持つ者に依頼
多くの事業者では外部委託が一般的で、その場合は点検費用も定期的に発生します。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要条件 | 契約電力50kW超(継続的) |
| メリット | 電気料金が安くなる |
| デメリット | 設備所有、点検義務、事故時の責任 |
| 主な機器 | 柱上開閉器、トランス、VCBなど |
| 点検 | 年次点検義務あり/主任技術者の配置必要 |
おわりに
高圧受電設備は、コスト削減につながる一方で、所有責任や点検義務などの負担も大きいものです。
導入を検討する際は、使用電力量、初期費用、維持管理の体制などを総合的に判断して進めましょう。
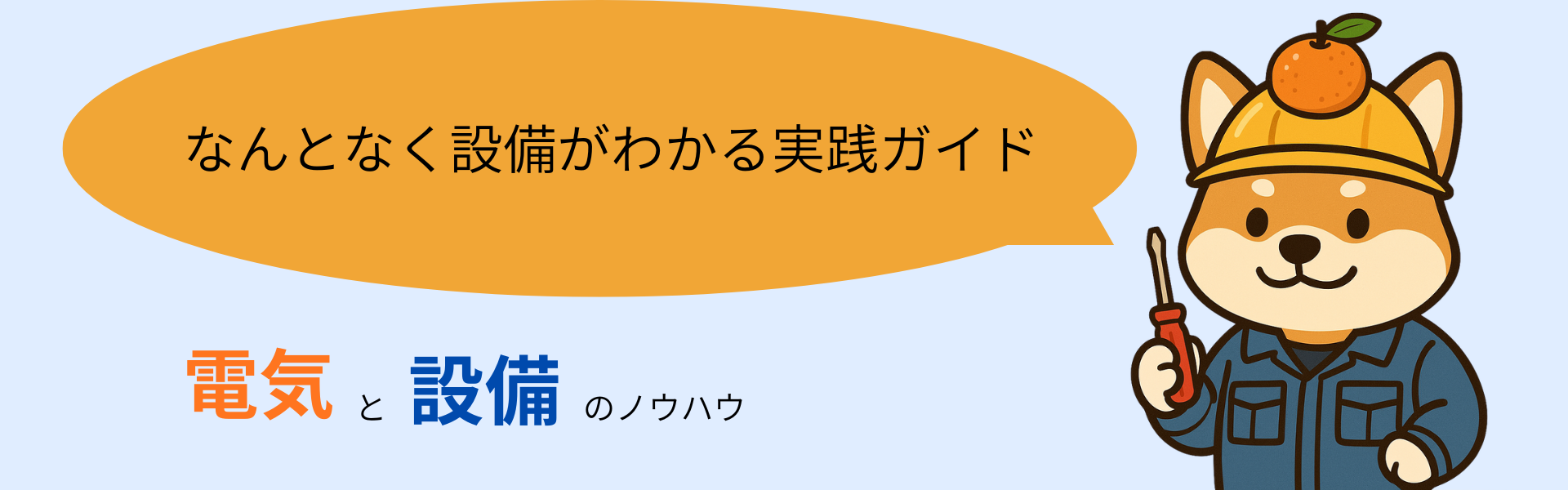

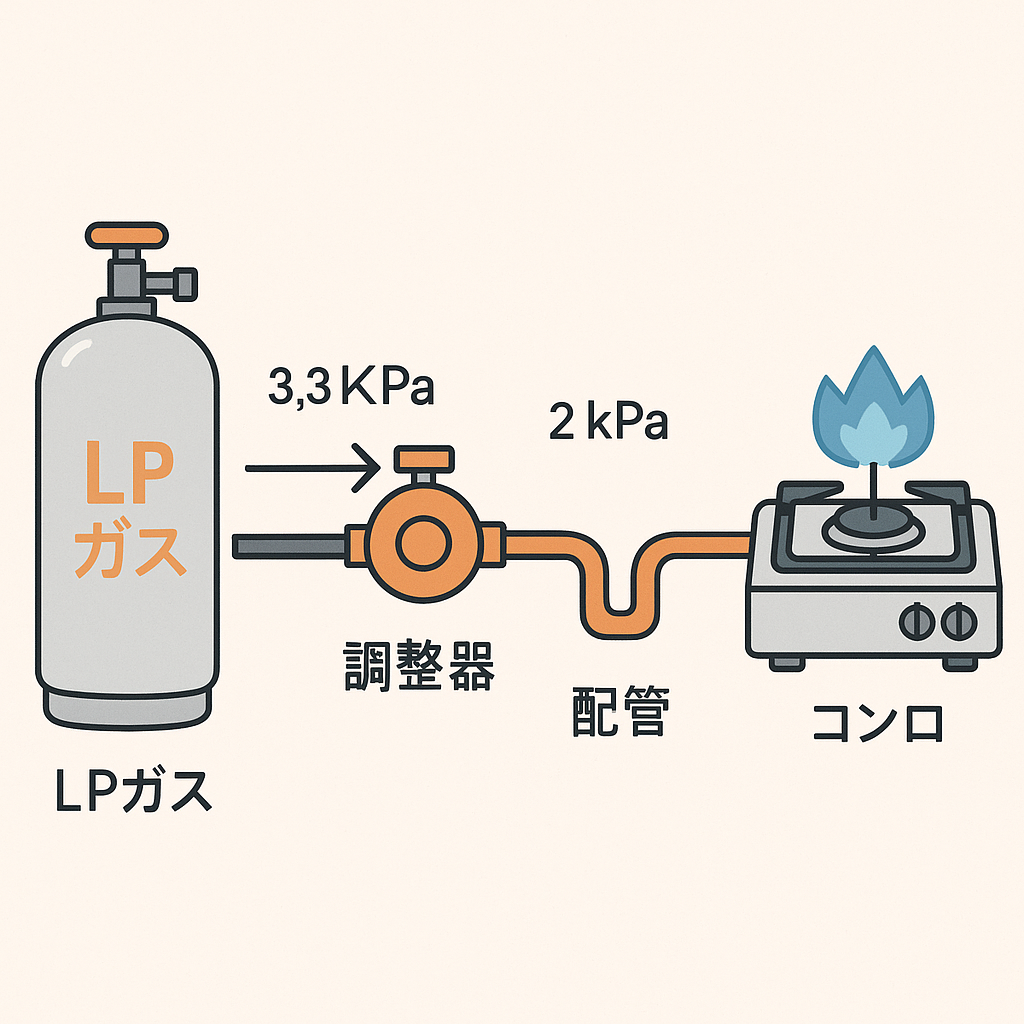
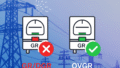
コメント