最近、太陽光発電設備を導入したところ、「なぜか漏電ブレーカーが頻繁に落ちる」というトラブルに直面していませんか?
「直流(DC)・交流(AC)側ともに絶縁測定しても異常なし。なのに、なぜ?」
その原因、実はインバータの中にあるIGBTトランジスタのPWM制御が関係しているかもしれません。
インバータと漏電ブレーカーの関係
太陽光パネルで発電された直流電力は、住宅や施設で使える交流に変換する必要があります。その変換を担っているのがインバータです。
インバータ内部では、**IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)を用いたPWM(パルス幅変調)**という方法で、擬似的に交流波形を作り出します。
このPWM方式は非常に効率が高い一方で、意図しない高周波成分も発生させてしまいます。
高周波ノイズと漏れ電流
この高周波は、配線や機器の絶縁体と地面との間にある浮遊容量(静電容量)に影響を与え、地面へ電流が流れるルートを作ります。これによって発生するのが漏れ電流です。
漏れ電流には主に2種類あります:
- I₀r(危険な漏電):絶縁不良や接触による感電や火災リスクのある電流
- I₀c(容量性漏れ電流):高周波によって静電容量を通じて流れる比較的安全な電流
太陽光発電設備で発生しているのは多くの場合、**I₀c(容量性漏れ電流)**です。絶縁抵抗値が十分であれば危険性は低く、感電や火災のリスクはほぼありません。
なぜ漏電ブレーカーが動作するのか?
問題はここです。
漏電ブレーカーはI₀dとI₀cを区別する能力がありません。
そのため、安全なI₀cであっても、「漏電」として誤認識し、ブレーカーが動作してしまいます。
どう対処する?
このような誤作動を防ぐには、以下のような対策が考えられます:
- 高周波ノイズフィルターの設置
- 太陽光発電対応の高感度誤動作防止機能付き漏電ブレーカーの採用
- アースの見直しや分割アースの導入
これらの対応により、誤作動を減らし、安定した運用が可能になります。
まとめ
太陽光発電設備での漏電ブレーカーの動作は、必ずしも「危険な漏電」ではない場合があります。インバータによるPWM制御による高周波ノイズと静電容量が原因の容量性漏れ電流であれば、危険性は低いですが、ブレーカーにはそれを判断する能力がありません。
もしお使いの設備で似たようなトラブルが起きている場合は、「本当に危険な漏電なのか?」を見極めるためにも、電気技術者への相談をおすすめします。
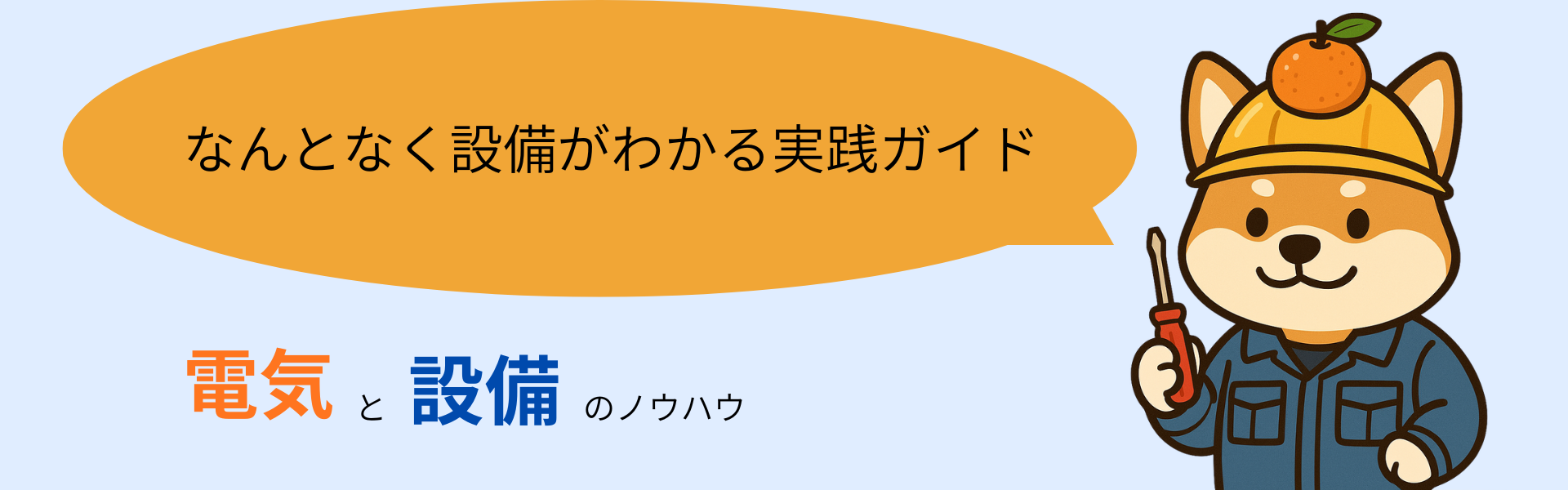
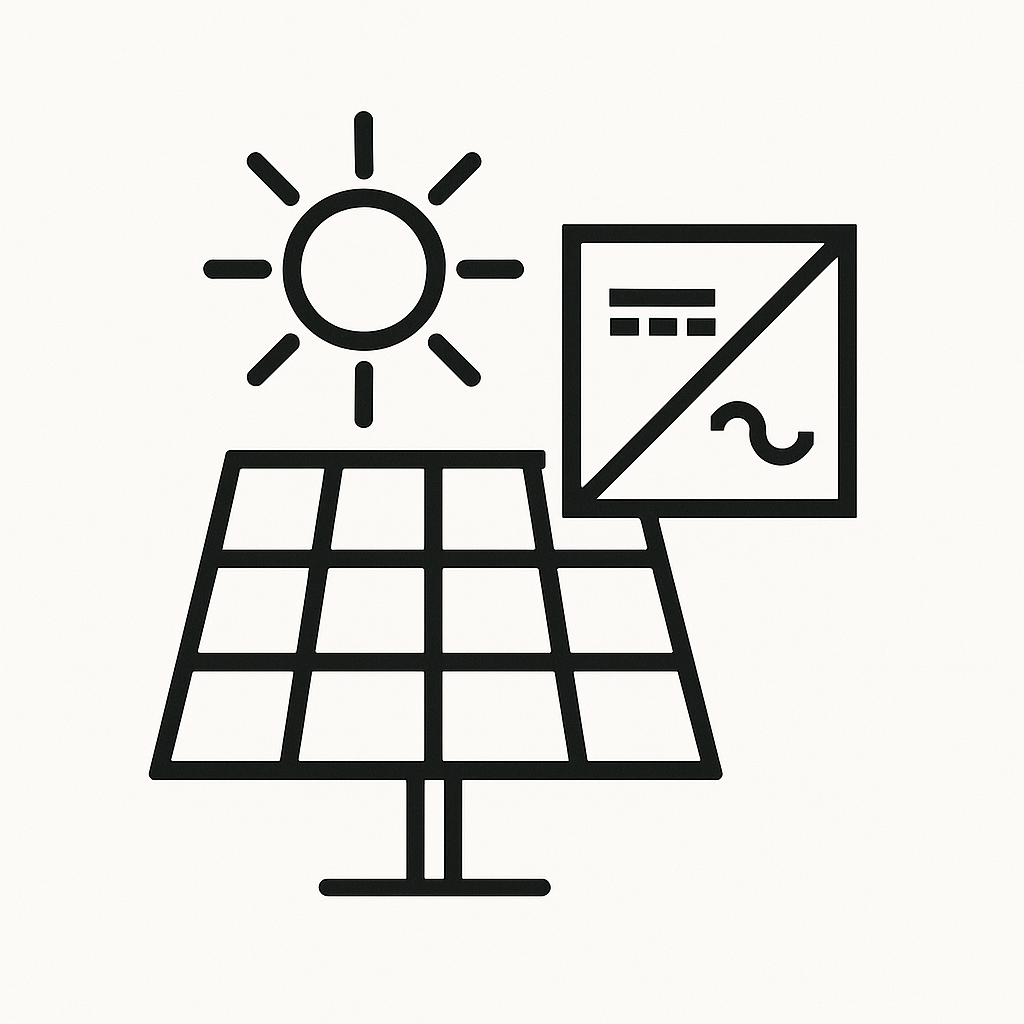
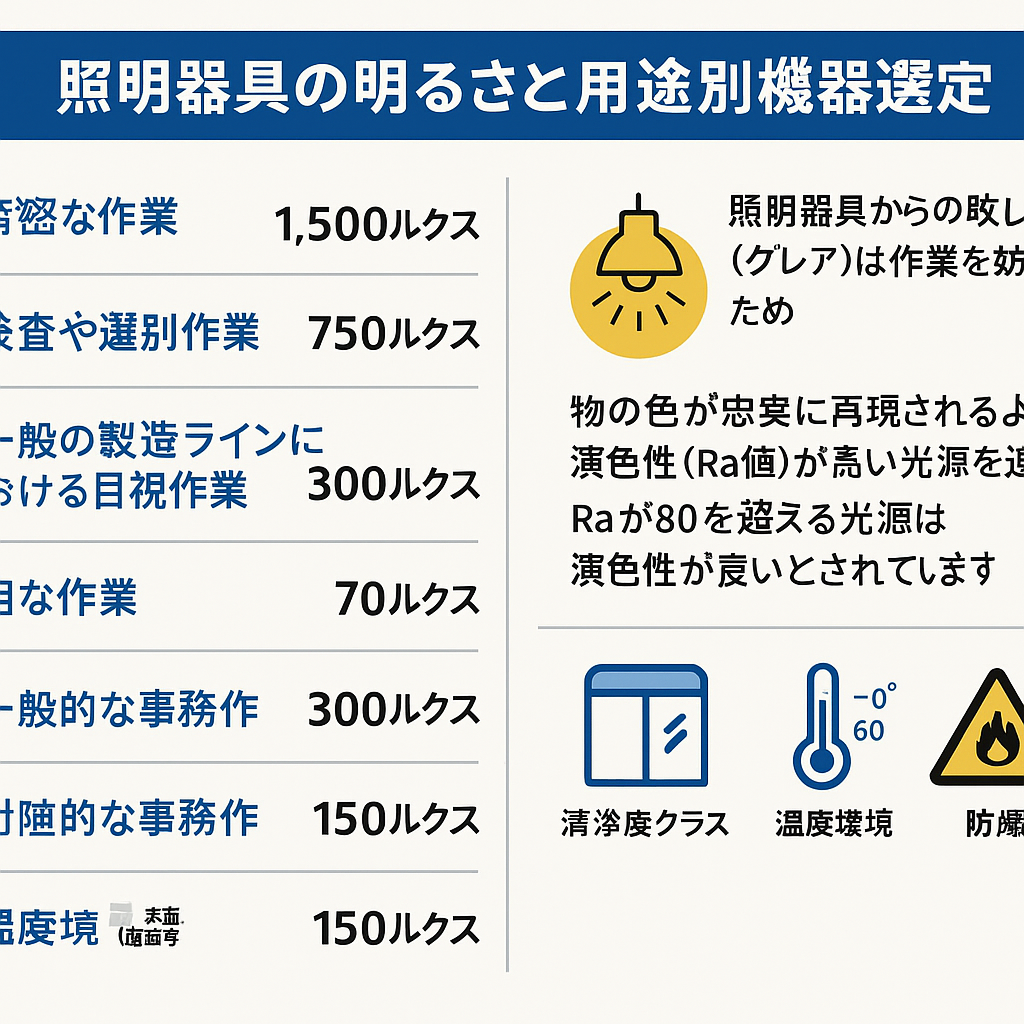
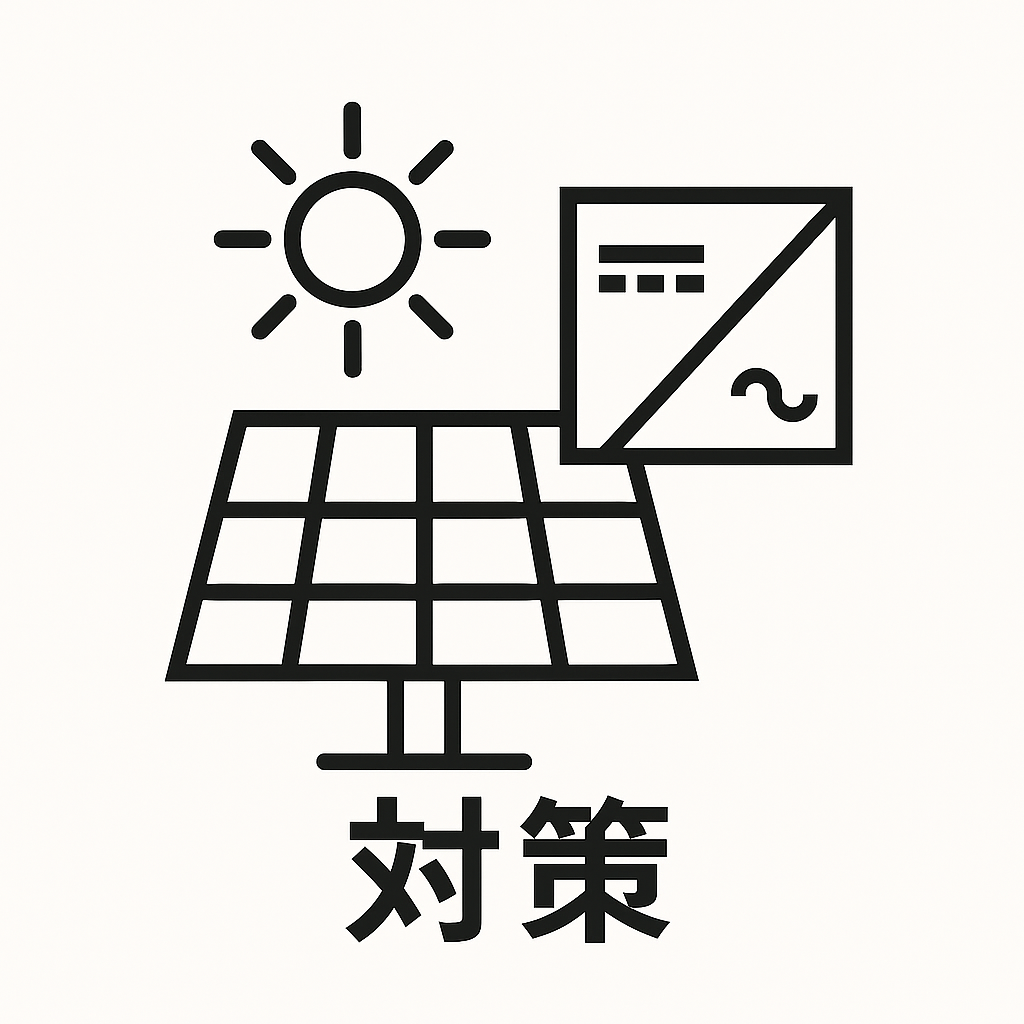
コメント